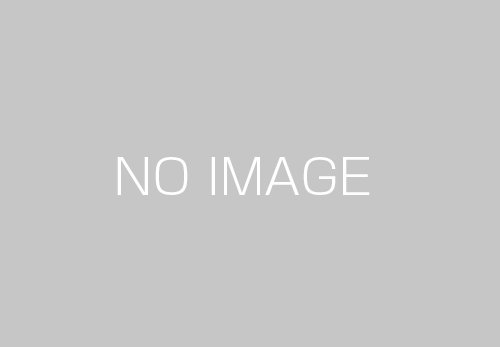目次
「葵祭」の起源はいつ頃?
「源氏物語」や「枕草子」にも登場した「葵祭(賀茂祭)」は、上賀茂神社と下鴨神社の例祭で、「祇園祭」「時代祭」とともに、京の三大祭とされています。

葵祭の起源は欽明天皇(531年即位)の頃に遡ります。
その頃、不順な天候が続き凶作をもたらし、また疫病が広まったため、天皇は両賀茂社に皇子を使わし祭礼を行いました。その結果、天候も平穏になり、疫病も収まったということです。
平安遷都の際には、賀茂両社は山城国と平安京の守護神として崇敬を集め、弘仁19(819)年、嵯峨天皇は葵祭を朝廷の公式行事に定めて内親王を賀茂の斎王としました。
藤原時代の儀式行装は、優美典雅を尽くす祭りとなりましたが、その後、変遷をたどりながらも、伝統の面影はそのまま今日に伝えてられています。

「路頭の儀」では、平安装束を身にまとった人々の行列が御所を出発し、下鴨神社を経て上賀茂神社へと練り歩きます。
「葵祭」は「祇園祭」のコンチキチンの賑やかさと比べるととても静かに行列が進みます。
音といえば、牛車のギシギシという音ぐらいで、時々、馬の鈴の音がするぐらいです。

葵祭の行列とは、どんなもの?
葵祭の行列は5つありますが、大きく分けて「勅使列(本列)」と「斎王代列(女人列)」の2つです。
「勅使列(本列)」
・ 警護の列
乗尻(のりじり)
検非違使志(けびいしのさかん)
検非違使尉(けびいしのじょう)
山城使(やましろつかい)
・ 天皇からのお供え物の列
御幣櫃(ごへいびつ)
内蔵寮史生(くらりょうのししょう)
馬寮使(めりょうつかい)
御馬(おうま)
牛車(ぎっしゃ)
・勅使列
和琴(わごん)
舞人(まいびと)
近衛使(このえづかい)
風流傘(ふうりゅうがさ)
・ 勅使のお供の列
陪従(べいじゅう)
内蔵使(くらつかい)
風流傘(ふうりゅうかさ)
「斎王代列(女人列)」
・ 斎王代列
命婦(みょうぶ)
女嬬(にょじゅ)
童女(わらわめ)
斎王代(さいおうだい)
采女(うねめ)
騎女(むなのりおんな)
内侍(ないし)
女別当(おんなべっとう)
蔵人所陪従(くろうどどころべいじゅう)
牛車(ぎっしゃ)

京都御所を10:30に出発し、丸太町通を東に向い河原町通を出町まで練り歩きます。
出町橋を渡り下鴨神社に11:40頃に到着します。
そこで、お昼休憩があり14:20に上賀茂神社に向けて出発します。
実は、この休憩時間は写真を撮るには最適です。
牛車なども止められていますし、お昼を早く済まされた方が写真撮影に応じてくれたりもします。
下鴨本通を北上し、北大路通を左折して西に進みます。
その後、賀茂川沿いを上がっていき御薗橋を渡って上賀茂神社に15:30頃に到着します。

この後、上賀茂神社にて祭儀が行われます。
葵祭といえば、5月15日の巡行のみと思われている方も多いかと思いますが、葵祭にさきがけて様々な祭儀が執り行われます。
葵祭の関連行事
賀茂競馬足汰式(かもくらべうまあしそろえしき)
5月1日13:00~ 上賀茂神社
5月5日に行われる賀茂競馬に先立ち、馬の年齢や足の速さを実際に疾走し、組合せを決定する行事。
烏帽子の浄衣の装束で騎乗し、本格的に馬にムチを入れ試走する。
流鏑馬神事(やぶさめしんじ)
5月3日13:00~15:30 下鴨神社
葵祭の前儀で、祭の露払いとして古くから行われてきた神事。
公家の狩装束の射手が疾走する馬上から矢を放ち、妙技を披露します。
神事は糺の森(ただすのもり)にある直線約400mの馬場を南から北へ砂塵を上げて疾走し、場上より100m間隔の3ヶ所に設けられた杉板の的に、矢継ぎ早に矢を番え射抜いていきます。
流鏑馬は、平安時代末期から鎌倉時代にかけて、武士たちの間で盛んに行われ、当時は鏑矢(かぶらや)を飛ばしていたので流鏑馬神事と呼ぶようになったそうです。

斎王代禊の儀(さいおうだいみそぎのぎ)
5月4日10:00~ 上賀茂神社・下鴨神社が毎年交互に斎行
葵祭の行装に奉仕するため。斎王代と女人50余名が身を清める儀式。
平安時代には、斎王には皇女または王女が奉仕しましたが、現在は、京都在住の未婚の女性が毎年選ばれます。
雅楽が流れる中、十二単に小忌衣をつけた斎王代は、神社の御手洗池に手を浸し清め、人形を流して罪穢れを祓います。
歩射神事(ぶしゃしんじ)
5月5日11:00~ 下鴨神社
宮中古式による葵祭の露払いの前儀。
弦(つる)の音で邪気を祓う神事。
鏑矢(かぶらや)で悪鬼を祓い、大的を射る神事や数々の弓矢の神事を奉納し、葵祭に関する全儀式が無事に行われるよう安全を祈る古式の弓神事。
賀茂競馬(かもくらべうま)
5月5日10:00~ 上賀茂神社
寛治7(1093)年に宮中で行われていたものを神社に奉納して以来続いている神事です。
内裏の女官たちが菖蒲の根の長短を競う遊びで、賀茂社の菖蒲の根が長く、価値を得たので、そのお礼参りとして競馬を奉納したのが起こりといわれています。
舞楽装束の騎手を乗せた14頭の馬が、約400mの馬場を二頭ずつ走り、その速さを競う左右の馬の競駈(きょうち)は、14:00頃から始まります。
賀茂競馬は、京都市登録無形民俗文化財に登録されています。
御阿礼神事(みあれ)
5月12日 上賀茂神社
葵祭の神霊を神山(こうやま)の裾の、榊で囲んだ神籬(ひもろぎ)に降臨を仰ぐ神事。
当日の夜、暗闇に中で「神迎え」をします。
千数百年前からの秘儀をそのまま伝えているといわれ、信仰の上からも、民俗学的にも非常に貴重な神事です。
具体的な祀りの諸事は、神に仕え、祀りを司る祭官のみが行うので、現在まで一度も公開されていません。
御蔭祭
5月12日9:00~ 八瀬御蔭神社、下鴨神社
葵祭にさきがけて、神霊を神馬に還して下鴨神社に迎えるための神事で、祭官、奉仕者約150人が、早朝下鴨神社を出発し、比叡山の山麓八瀬御蔭神社に向かいます。
古代の信仰形態を今に伝えています。
糺の森では「切芝神事」が厳かに繰り広げられ、6人の舞人が神馬に向かって優美な舞楽の「東遊(あずまあそび)」を奉奏します。